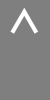患者さま宅を訪問して
「60年がんばってきて、やっとこれから好きなことできるなーって思ってた矢先にこんな目にあっちゃって…」
ボソッとつぶやいた患者さまの横で、苦楽を共にしてきた奥様が目を腫らし、タオルで涙をぬぐい続けていました。
22歳という若さで生まれ育った新潟を後に、未開拓のこの地に渡ってきた彼は、この大地を愛し、開拓という大仕事に鍬ひとつで挑み、やがて酪農を立ち上げ長年に渡り苦難の道を歩んできました。
私がこの患者さま宅の訪問を切望したのは、癌の終末期という診断が3ヶ月前にあり、主治医から厳しい説明を受けているにもかかわらず「病気が勝つか、自分が勝つかだ」と話されていた言葉が印象的で、訪問するにはかなり遠いところでしたが、周囲の協力を得て訪問へ行かせていただきました。
片道40分以上かけてたどり着いたその土地は、広大という言葉がぴったりの広々とした大地で、開拓の力強さと苦労を想像させました。
笑顔で迎えてくれた患者さま。開拓で培われた忍耐強さを感じさせる、ゆっくりとして丁寧な口調で今の無念な気持ちを語ってくれました。
そしておもむろに出してきた開拓史の本をめくり、当時の写真と開拓の様子が書かれたページを見せてくれました。そこには決して立派とはいえない藁葺の小屋のまえに意気揚々と立ち、白い歯をのぞかせ、希望に満ちた若き日の姿がありました。
誇らしげに見せる彼の姿に、奥様の涙でぐしゃぐしゃになった笑顔がみられました。
「この頃は良かったなー。朝方まで盆踊りして昼間寝たっけなー。戻りてーなー…」
現在は息子さん、お孫さんの3代に渡って守り続けてきた酪農は大切に受け継がれています。「感謝。感謝だ…」と、何度もつぶやく彼の姿に、同席のお嫁さんが目に涙を浮かべていました。
近年、終末期患者の在宅療養や、在宅での看取りが増えつつあります。
当院内科外来でも、1週間から2週間に一度の通院で出来るだけ住み慣れた安住の自宅で療養したいという終末期の患者さまが数名いらっしゃいます。
今回の訪問で学んだことは、私たちが時間に追われ、忙しいなかでお聞きすることは、その人の人生の中のほんの一部でしかない、ということでした。
医療者にとって彼は「癌の患者」。
家族にとっては「この土地を切り開き、発展させてきた尊敬すべき夫であり、父」である、という認識のズレがあっては、決して看護師として寄り添うことはできません。
私達は、まずその人の歴史を学び、敬意を持って看護していかなければならないということを今更ながら痛感し、胸が熱くなる訪問でした。